- webディレクター
- フロントエンドエンジニア
- オープンポジション
- 他42件の職種
- 開発
-
ビジネス
- webディレクター
- テクニカルディレクター
- Webディレクター/実務経験無
- Webディレクター/プロマネ
- Webディレクター
- リモート/プロジェクトリーダー
- コンテンツディレクター
- ディレクター
- 企画・制作ディレクター
- Webディレクター
- 企画・運用Webディレクター
- Webディレクター(業務委託)
- ディレクター・プランナー
- ディレクター/マーケティング
- Webディレクション
- 経理・会計
- 経理・財務
- 総務
- アカウントプランナー
- 採用広報
- SNS運用アシスタント
- マーケティング・PR
- SNS運用ディレクター
- SNS運用インターン
- SNS運用
- Webマーケター/ディレクター
- デジタル広告の企画・運用
- デジタルマーケティングの提案
- 社会人インターン|副業ライター
- webメディアライター・編集
- その他
「持続可能な開発目標(SDGs)」があらゆるところに掲げられ、さまざまな社会問題への関心が高まる中、「仕事を通じて社会貢献したい」と考える若者が増えています。
彼らが考える「社会貢献」とは、環境破壊や経済格差といった「社会問題を解決すること」。しかし、実際に会社の仕事で実現できることは、直接的な社会問題の解決にはつながらないことがほとんどです。
若者と会社が考える社会貢献とのギャップはどこにあるのでしょうか? また、日々の仕事で実現できる社会貢献とはなんでしょうか? デジタルエージェンシーTAMの爲廣慎二社長と、しゃかいか!代表の加藤洋さんとともに考察します。
「人の役に立ちたい」
―若い世代で社会貢献に対する欲求が高まっていますね。
爲廣:ここ3〜4年ぐらいですね。履歴書の「この先やってみたいこと」の欄に、「社会貢献がしたい」とか「人の役に立ちたい」というようなことを書かれる方がすごく多くなっています。
20代の若い人たちに絞ると、おそらく半分ぐらいの方がそういうことを書いている感があって。最初見たときは、「履歴書用に見栄えがいいから書いているのかな」と思ったんですけど、「それが違うな」と思ってきたのがこの1〜2年ぐらいですかね。
社会貢献的なことが重要視されている中で、TAMができる社会貢献とはなんなのか?といったことを、このところずっと考えています。

加藤:今の20代くらいの人たちは、学校の授業の中でSDGsやESD(持続可能な開発のための教育)を受けていて、小さいころから日々のニュースでも地球温暖化、格差問題、高齢化といった社会問題をずっと聞き続けているから、そもそもそこに対する意識は僕らが想像できないほど高いんだろう、と思いますね。

爲廣:今の若い人たちは金銭的な報酬よりも、社会貢献や自己成長といった「感情的報酬」を重視しているという記事も読みました。この「感情的報酬を求める」ということは「自己実現を求める」ということとイコールだと思います。
自己実現とは、僕の理解では「利己的なんだけど正しい行い」で、「なにかしらの見返りを求める活動」。そして、その見返りとは、「楽しい」とか「人の役に立っている」とか、そういう感情的報酬だと思うんですね。
「マズローの欲求5段階説」では、人間の欲求が「生理・安全・社会・承認・自己実現」の5段階に分けられていますけど、今の世の中、だいたいの欲求はもう満たされているから、最後の「自己実現」を求める段階に来ている人が多いということでもあると思います。
社会貢献のリアル、必要なスキルと人脈
―そんな潮流の中、加藤さんのチームでは直接的に社会貢献につながるようなプロジェクトに取り組まれていますよね?
加藤:プロボノとして関わっているプロジェクトに「ノカテ」と「一坪茶園」というプロジェクトがあります。
「ノカテ」の方は跡継ぎがいなくて、どんどん畑が荒れてきている福井県・越前水仙の風景をなんとか次世代につなぐ取り組み。僕よりちょっと下の世代と一緒に活動しています。

水仙は生け花に使われているんですが、生け花用だと出荷基準がとても厳しくて、続けていけない仕事になっていたんです。それをブーケにするなど新しい楽しみ方を提案することでなんとか持続できないか模索しています。銀座の「無印良品」で展示販売会をやったりもしました。
「一坪茶園」の方も、後継ぎがいなくて消滅危機にある静岡の茶畑を支援する活動ですね。今、社外のメンバーと一緒にお茶の販路を海外に広げたり、水出しで手軽に飲めるような商品にしたり、お茶に新しい価値をつける活動をしているんです。
爲廣:そういうふうに社会課題を解決していくべきだとは思うんですけど、その水仙とかお茶を持続可能にするような社会貢献をしようと思うと、なにかしらのスキルを身につけんとあかんやろうな、と思いますね。
若い人たちは社会課題を解決する仕事に就くのと、自分のスキルを成長させるのとを両立させたい人がほとんどだと思うんですけど、社会貢献と自分の成長するプロセスをすぐに結びつけられるほど、社会貢献は甘くないというか……。
加藤:まさにそうで、「社会課題を解決します。だから力を貸します」みたいなことを言っても、自分たちが後継ぎになって当事者になるわけでもないし、だったらなおさら生半可な気持ちではできなくって。

「一坪茶園」の活動なんかでも、メンバーは本業でスキルや人脈を築いたベテランの方が中心になっています。
実際にお茶農園が減少するマクロな動きは止められるか分からないけれども、なんとかしたいという気持ちで、自分たちのスキルを持ち寄って頑張っているという感じですね。
爲廣:「社会貢献」って実際に目の前で困っている人を助けるということだけじゃない。そういうスキルを持った人たちを育てるということも、めちゃくちゃ立派な社会貢献のはずなんですよね。世の中、直接的に社会課題を解決する仕事をしている会社なんて、そうたくさんはないですから。
TAMの仕事は、Webサイトの構築とかアプリの運用だったりがメインですが、そういうクリエイティブワークができる人を1人でも多く増やすということが、TAMの社会貢献だと思っています。
大事なのは「誇りを持てる仕事」を選ぶこと
―「社会貢献」というのは、直接的な社会問題の解決だけではなく、間接的なものもあるということですね。
加藤:それで言うと、僕らはいろんな企業や組織の活動をデジタルでお手伝いしていますが、誇りに思える仕事を選んでいるというのはありますね。「これは社会に価値を生み出しているのか?」「社会的に貢献しているのか?」という判断が入っていると思うんですよね。
爲廣:公序良俗に反するような仕事は絶対にしません。「家族に誇れる仕事をしよう!」というのは、TAMの理念にも入っていますから。

これはハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱した「クリエイティング・シェアード・バリュー(CSV:共通価値の創造)」の考え方にもつながりますね。
社会課題を解決するような活動と、利益を生む活動を両立させること。経済的な価値を生み出しながら、社会のニーズも取り込んで社会的価値も生み出すアプローチですね。
自分たちがやっていることがただの金儲けでなくて、社会に役立つというふうに考えてやっていると、アウトプットするものや次につながることというのも、これまでとは変わってくる気がしますね。
加藤:それこそCSVの中では、実はデジタルトランスフォーメーションやソーシャルメディアなどはすごく重視されているんですよ。
デジタル経済の進化の先にある社会では、今まで時間や場所などの制約でできなかった経済活動や社会活動が低コストで、しかもネットワーク力で幅広く展開することができる。先端技術によって、⼈と企業、人と社会の関係のあり⽅がどんどん作り直されているんですね。
ですから、デジタルスキルを身につけるというのは、CSVや社会にとても貢献できる可能性が広がると思っています。だからTAMのような会社で揉まれたり、いろいろ考えたり、目の前の仕事を頑張ったり……というのは結局、社会貢献につながると思いますね。
―つまり、若い人にとっては、普段の仕事の中でスキルを身につけたり、人脈を広げたりすること自体が社会貢献であると。
爲廣:そうですね。日々の成長は社会貢献そのものだと思います。
そういう意味で、TAMができる社会貢献というのは、1人でも多く「勝手に幸せになれる人を増やすこと」なので、僕はそこに邁進せなあかんと、さらに決意を固めました。
そして、その自分が成長するプロセスを楽しんでもらうこと。「楽しむ」って、若い人たちが求める感情的報酬そのものでもあるので。ちなみに加藤さんはどんなときに感情的報酬を感じますか?

加藤:僕はインターネットの可能性をすごく信じていて、いろんなプロジェクトを通じてその可能性にチャレンジができることにやりがいを感じています。
例えば、都会ではなく地方の過疎が進んでいる地域などに移住して、地域のために活動している若い人たちにデジタルマーケティングの仕事を依頼して活躍してもらっています。
もう5年ほどトライしていますが、場所を選ばずできる仕事も多いので、地方でも食べていける若い人を増やせると実感しつつあります。
爲廣:なるほど、そういうことを仕掛けているとやっぱり面白いし、自分も成長しているという感覚はありますよね。
「チャレンジをしていくこと」って、やっぱり一番最初の大きな感情的報酬なんですよね。正しい利己的な行動だと思うので。それをTAMは全力で応援する文化があります。
どんどんスキルと人脈を広げて、日々の成長を楽しむことで社会貢献していってほしいと思います。

[取材] 岡徳之 [構成] 山本直子 [撮影] 藤山誠
/assets/images/5818/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1495011949)



/assets/images/1871705/original/2a9b4e0f-adf7-4af5-88d4-ab1e6e197ae7?1542249372)

/assets/images/5818/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1495011949)
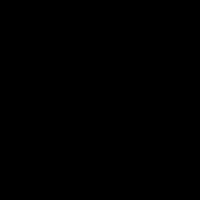



/assets/images/3478188/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1549953460)
