- PdM(マネージャー候補)
- フルスタックエンジニア
- Team+CS
- 他38件の職種
- 開発
-
ビジネス
- PdM(マネージャー候補)
- PdM/プロダクトマネージャー
- テクニカルPdM
- 新卒採用メンバー
- 【経営管理部】経営企画
- コーポレートIT
- セキュリティエンジニア
- 情報セキュリティマネージャー
- 労務・総務
- 人事/カルチャー推進
- 新規事業開発担当
- Team+アカウントエグゼ
- Findy Team+事業FS
- グロース戦略推進
- 事業企画・推進担当
- 事業推進/ビジネスグロース
- FindyCareer:USL
- FindyCareer:CSL
- FL:ユーザーサクセスリーダー
- FL:ユーザーサクセス
- 転職:USキャリアアドバイザー
- toCマーケティング
- toC/toBマーケティング
- toCマーケティング担当
- BtoBマーケティング
- マーケマネージャー候補
- その他
ファインディは「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」をビジョンに、ITエンジニアと企業のマッチングやエンジニア組織向けSaaSの開発などエンジニアの成長を支援するプロダクトを複数展開しています。
「元々、エンジニアとしての成長モチベーションは決して高くなかった」——そう語るのは、ファインディのプロダクト開発部で副部室長を務める浜田直人さん。新卒でSIerに入社し、2社の事業会社を経てファインディへ。
キャリアの変遷を通じて何を学び、どのように価値観が変わったのか。そのストーリーとともに、「最高の開発環境の実現」に向けた取り組みについて迫ります。
プロフィール:浜田 直人
新卒でSIerに就職後、Web系企業やスタートアップを経て、2022年5月にファインディへ参画。現在はFindy Team+の開発に携わりながら、EMとして開発チームのマネジメントを担当。開発者体験を向上させながら、開発生産性を高める方法を日々探求している。
目次
SIerからのキャリアスタート、エンジニアとしての価値観を変えた出会い
事業会社への転身と技術力の成長
ファインディとの出会い、新しい挑戦の始まり
最高の開発生産性と開発者体験を目指して
SIerからのキャリアスタート、エンジニアとしての価値観を変えた出会い
エンジニア組織の開発生産性可視化・向上SaaS 「Findy Team+(チームプラス)」のプロダクト開発部にて副部室長を務める浜田さん。エンジニアとしてのキャリアはSIerからスタートしました。
浜田:
大学の情報系学科を卒業後、新卒で700名規模のSIer企業に入社しました。きっかけは就職活動中に参加した業界研究のセミナーで、「情報系の学生の90%以上がSIerやシステムエンジニアになる」というデータを見て、自然とその選択肢を意識するようになりました。
それをきっかけに、IT業界を中心に企業を探し始めましたが、正直なところ、当時は仕事に対して特に強い意志があったわけではなく、大きな流れに流されるような感覚でした。
入社後、様々なプロジェクトに関わりながらWeb開発の経験を積んでいきます。
浜田: その会社ではWeb系のアプリケーションを開発する部署に配属され、主にB2BのWebプロダクトを開発していました。ただ、受託開発を行う形だったため、Web以外にもデスクトップアプリを作ることもあれば、インフラ構築を担当することもあり、多岐にわたる業務に関わりました。 私が関わったプロジェクトは、比較的短期間のものが多く、長くても1年ほどのスパンでした。プロジェクトが終わると次の案件に移る形で、1年のうちに2つの異なる仕事を経験することも珍しくありませんでしたね。
いくつかの厳しいプロジェクトを乗り越えてきた経験もあるそうです。
浜田:
ある出向先のプロジェクトでは、私と先輩社員の2人で参加していましたが、チーム全体はフリーランスや他社のメンバーを含めて5人ほどの少人数で構成されており、見積もりが厳しかったのか、そもそものスケジュールに無理があったのか、最初からプロジェクトが完了するイメージが湧かないような計画で進行していました。
当時は出向先の方と毎日進捗会議がありましたが、スケジュールを守ることが必須でありリスケは許容されない状況でした。そのため労働時間を延ばすことでカバーするしかなく、常にプレッシャーを感じながら仕事をしていました。その後、先輩が体調を崩してしまったのですが、「同じ会社のメンバーのタスクは、できるだけ同じ会社の人がやるべき」という暗黙のルールがあったため、結果的に私自身の負担が大きくなったこともありました。今ではこういった状況は少なくなったと思いますが、当時は色々と苦労したことを覚えています。
苦労を経験した一方で、自身のエンジニアキャリアの転機となる出会いがありました。
浜田:
現場では大変なことも多かったですが、最後までプロジェクトに残ったメンバーとは、自然と意気投合するようになりました。苦労を共にしたからこそ、強い絆が生まれたのかもしれません。
また、チームには1人フリーランスの方がいて、その方の技術力は本当に圧倒的でした。その方は他のメンバーの倍の速さで実装を進めており、その姿を間近で見て「できるエンジニアってすごいな」と圧倒されると同時に、自分ももっと成長したいという強い気持ちが湧き上がってきました。
これまで、仕事に対するモチベーションがそこまで高くなく「プログラムを書くのが好き」というタイプでもなかった私にとって、その経験は今後のキャリアやエンジニアとしての成長を考えるきっかけとなりました。
「もっとエンジニアとして成長しなければ」と強く思うようになり、モチベーションも一気に上がったターニングポイントだったと思います。
事業会社への転身と技術力の成長
ある経験をきっかけに事業会社への転職を考えるようになります。
浜田:
SIer企業で約9年間働いた後、事業会社への転職活動を始めました。きっかけは、あるプロジェクトで事業会社の開発チームへ業務委託として出向した時の経験です。
そこで、エンジニアがビジネスサイドのメンバーと密に連携し、事業の状況に応じて開発の優先度が柔軟に入れ替わる環境を目の当たりにしました。運用中のシステムでエラーが発生すれば、開発を一時中断して全員で最優先で対応にあたる。何よりも、事業会社の社員の「自分がやったるぞ!!」という熱意を間近で感じ、圧倒されました。
これまで業務委託として当事者から一歩引いた立場で開発に関わっていた自分にとって、全員が自分ごととして仕事に向き合う姿勢は衝撃的でした。
この経験をきっかけに、事業会社のエンジニアとして働きたいと考えるようになりました。
事業会社への転職活動では、これまでとの意識の違いに直面し、苦戦します。
浜田: 当時、サイバーエージェントやDeNA、グリーなど、いわゆるメガベンチャーの事業会社が勢いを増している時期で、そうした有名企業を中心に応募しました。しかし、いざ挑戦してみると想像以上に厳しく、結果的に多くの企業に落ちてしまいました。 正直、SIerから事業会社への転職がこんなにも難しいとは思っていなかったので、かなり辛かった記憶があります。苦戦した理由は、自分自身のスタンスや意識にあったことに後から気付きました。当時の私は、プログラミング言語や技術そのものに強い興味を持っていたわけではないのと、SIerではプロジェクトごとに使用する言語やフレームワークが異なることが多く、「その現場で使われているものを覚えればOK」というスタンスでした。
しかし、事業会社では状況が全く異なります。技術選定を自分たちで行い、最新のトレンドをキャッチアップしてプロダクトに反映させていく文化が根付いていました。そこで初めて「技術を能動的に学ぶ姿勢」の重要性に気付かされ、自分にはその前向きな姿勢やキャッチアップ力が足りないことを痛感しました。 初めての転職活動では苦労しましたが、最終的には食べログを運営するカカクコムからオファーをいただき、転職を決意しました。
カカクコムに入社後、大規模なシステム開発に携わり、仕事の進め方や考え方にも変化があったと語ります。
浜田: カカクコムで最初に配属されたチームでは食べログの「レビュー機能」をはじめ、主にユーザーがログイン後に利用する機能開発を担当しました。 特に印象に残っているのは、忘年会や歓迎会シーズンなど、多くのユーザーが訪れるタイミングに合わせたプロジェクトです。限られた期限内で機能開発を進める必要があり、プレッシャーも大きかったのですが、多くのユーザーが利用する大規模なシステム開発に関わることができ、その後に繋がる貴重な経験を得ることができたと思います。 仕事の進め方についても新たな気づきを得ることができました。SIer時代は納品が最優先で、小さなバグでもすぐに修正しなければならない環境でした。しかし、カカクコムのような事業会社では、完璧を求めるのではなく、ユーザーにとって価値のある開発とそのスピード感を重視する傾向があります。1つ1つの完成度よりも、ユーザーにどれだけ価値を還元できるか、という観点で優先順位をつけるようになり、私自身の開発における意識や考え方も大きく変わりました。
技術力向上への意識も自然と高まっていきました。
浜田: カカクコムでは、5年間Ruby on Railsを使って開発を行っていましたが、バージョンアップや新機能を通じて新たにできることを学び、自然と技術の最新情報を追うようになりました。以前はそれほど意識していなかった技術への興味や探求心が、次第に強くなったんです。 また、当初はテストコードを書く機会がほとんどありませんでしたが、途中で挑戦してみたところ、非常に良い成果が得られました。テスト自動化の重要性をチーム内で共有して、最終的にはテストコードをプロジェクト開始時から導入する方針を固めるに至りました。 カカクコムでの5年間は、意識面でも技術面でも大きく成長できた貴重な時間だったと思います。
カカクコム時代
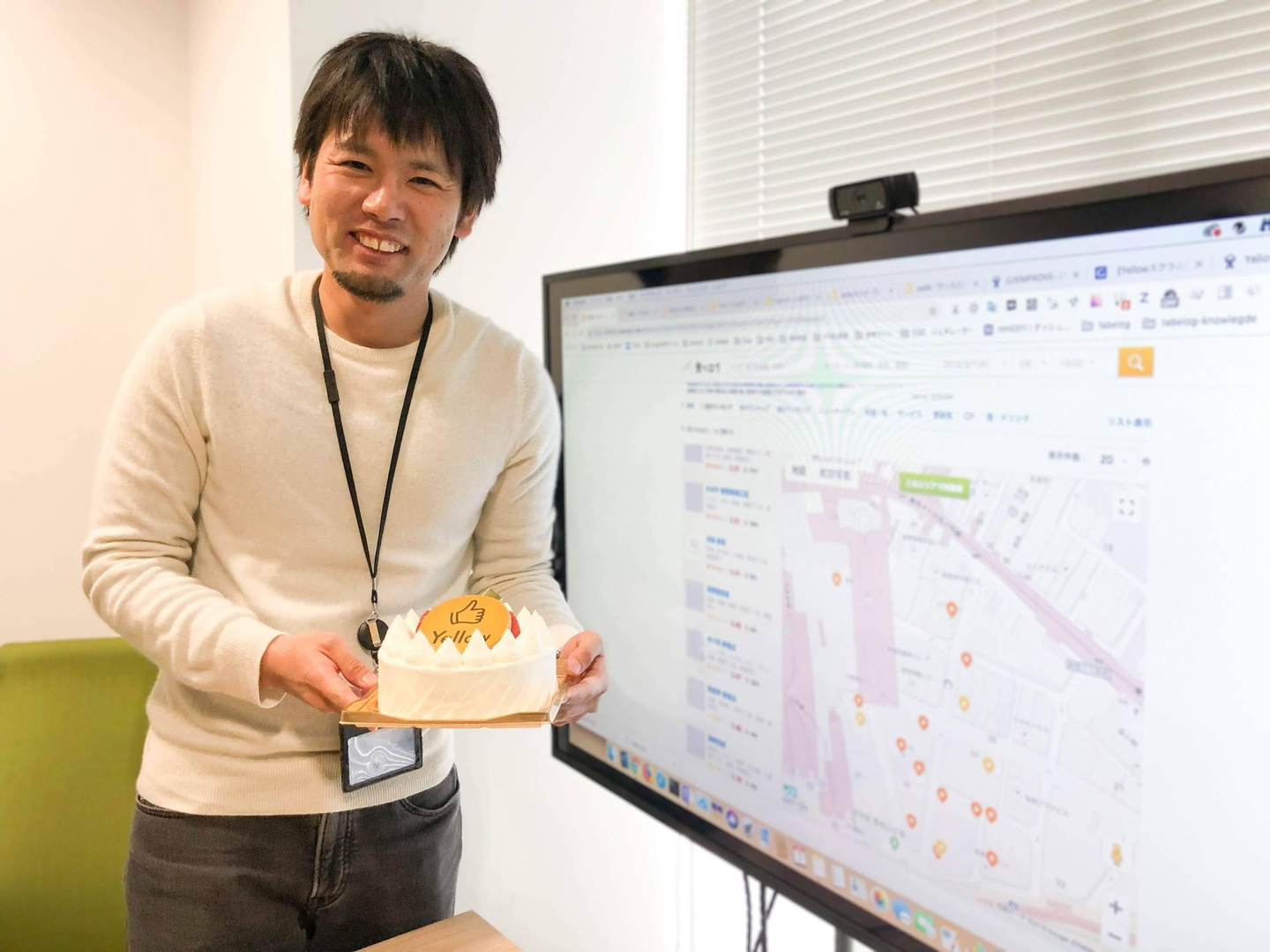
ファインディとの出会い、新しい挑戦の始まり
カカクコムを退職後、スタートアップ企業での経験を経て、2022年にファインディにジョインします。きっかけは、転職プラットフォーム"Findy"上で受け取ったファインディからのスカウトでした。
浜田:
カカクコムを退職した後、新規サービスの立ち上げに携わりたいという思いから、比較的フェーズの浅いスタートアップ企業に転職しました。カカクコム時代にサービス立ち上げ初期に携わったエンジニアの方から当時の話を聞き、非常に興味深く感じたことがきっかけです。その話を聞くうちに、自分もそういった経験をしてみたいという気持ちが芽生えました。
その会社ではエンジニアが少なかったため、最初は自分一人で全てを担当する形で進めていました。この自由さは最初は楽しかったのですが、次第に「誰かと一緒に考えながら開発を進めたい」という気持ちが強くなっていきました。自分の考えが常に正しいわけではなく、他のエンジニアと意見を交換しながら進めることで新しい視点を得られることの重要性に気づいたからです。もう少し規模が大きく、チームでの議論が活発な会社に移りたいと考えるようになり転職活動を始めました。
そんな中、なんとなく登録していた転職プラットフォームの”Findy”の中でファインディから採用スカウトが届き、興味を持ってカジュアル面談に進みました。
組織のフェーズや開発体制を強化していく姿勢に共感し、ファインディで働くことを決めました。
浜田:
ファインディに興味を持ったのは、自分の求める環境にマッチしていたからです。大きな組織に1メンバーとして入るより、これから開発体制を整えていくフェーズに関わりたく、そうした規模感の会社を探していました。
当時、ファインディは社員数70人ほどで、自分にとってちょうど良い規模感でした。前職では50人ほどに増えるタイミングで働いていましたが、ファインディは整いすぎず小さすぎず、自分の力を発揮しやすいフェーズだと感じました。さらに、カジュアル面談でこれからエンジニア採用を強化し、成長していこうという意欲が強く伝わってきたのも大きなポイントでした。そうした成長フェーズに関われることに魅力を感じて最終的に入社を決めました。
「成長している企業で働きたい」という気持ちは当時から強かったですね。もちろんファインディもスタートアップなので、この先の成長は未知数でしたが、開発体制を拡大してより良いプロダクトを作っていこうとする姿勢に「この会社なら可能性がありそうだ」と思えました。
事業への興味もありましたが、それ以上に採用への本気度や成長意欲に惹かれた部分が大きかったです。
入社後、現場で成果を上げながら1年後にチームリーダー、その後副部室長となりマネジメントという新たな挑戦にも取り組むことになりました。
浜田:
入社後は、エンジニア組織の開発生産性可視化・向上SaaS 「Findy Team+」の開発を担当しました。前職でも使っていたRubyとTypeScriptメインの開発環境だったので、技術的な面で言えばキャッチアップには問題がなく、特に立ち上がりで苦戦することはなかったと思います。
入社から1年半後、チームリーダーに昇進し、その後副部長としてマネジメント業務にも携わることになりました。最初の1年半でプレイヤーとして実現したいことは大体達成できたと感じており、その後は組織が拡大していく中で、開発パフォーマンスを維持しながら、どのようにチームをスケールさせるかを考える機会が増えました。チームビルディングや組織作りに取り組む必要性を感じていた中で、その結果として役職がついてきたという感じです。
最高の開発生産性と開発者体験を目指して
現在の組織課題を踏まえて、今後は組織の成長を支える体制づくりに注力していきたいと考えています。
浜田:
組織規模が大きくなると、従来の体制をそのまま維持するだけではさまざまな問題が発生します。例えば、チームを分ける必要がある中で、横の連携をどのように強化するかといった事です。
また現状として、エンジニア採用には力を入れていますが、採用後のマネジメントや育成がまだ十分に仕組み化されていないという課題があります。
メンバー育成をチームリーダーに委ねるだけでなく、メンバー一人ひとりの状況を正確に把握し、モチベーションの低下やその他の問題に適切に対応するためには、管理体制をより仕組み化し、複数の責任者が協力して管理していく必要があります。
今後は、組織連携の強化やピープルマネジメントの仕組み化に取り組みながら、サステナブルな形で組織をスケールさせていきたいと考えています。
これは私自身の過去に経験した困難から来る思いでもありますが、すべてのエンジニアが心地よく働きながら、成長と成果に向き合える最高の環境を作り上げていきたいと考えています。
その先にある「Findy Team+」のプロダクトとしての目標については、次のように語ります。
浜田: これは入社当初から言っていることですが、開発エンジニア組織の技術スタックに「Findy Team+」がマストツールとして挙げられる存在になりたいと考えています。 プログラミング言語やフレームワーク、テストツールと並び、当たり前に使われるツールにしたい。イメージとしてはGitHubや、可視化ツールという意味ではDatadogのようなエンジニアにとって欠かせないポジションを目指しています。
最後に、候補者へのメッセージを伝えてもらいました。
浜田: ファインディはエンジニアドメインに特化した事業展開をしているからこそ、最高の開発生産性と開発者体験を実現する環境を目指しています。この環境で得られるノウハウやスキルは、どこでも活躍できるエンジニアになるために必ず役立つと確信しています。 新しいチャレンジをしたい方は、ぜひファインディをご検討ください!

/assets/images/18609226/original/e2cf5627-ecac-410f-90fe-b09d5086a50d?1721186318)
/assets/images/18609226/original/e2cf5627-ecac-410f-90fe-b09d5086a50d?1721186318)


