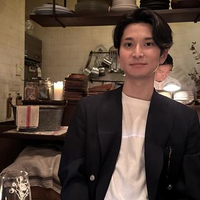※このストーリーは、noteで発信した記事を転載しています。
はじめまして! 株式会社カンリーでエンジニア採用をしている宮本です。
カンリーでは、「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」というミッションを掲げていますが、
・ミッションの実現に向けて、どんなことをしているのか
・誰に、どんな価値を提供して、どんな社会(世界)を作りたいのか
・どんなプロダクトを開発しているのか
といったことを、これまできちんとお伝えできていなかったかなと感じています。
そこで今回から、代表、CTO、CIO、CPOなどボードメンバーのみなさんに、”カンリーの未来”について、さまざまな観点でお話しをお聞きしたいと思います。
第1回目は代表の辰巳、CTOの小出に、カンリーが目指す世界と実現に向けた課題について、話していただきました。
代表取締役Co-CEO 辰巳 衛
早稲田大学卒業後、双日株式会社(旧日商岩井)に入社。与信・事業投資の審査、パラオ国際空港、下地島空港など国内外の空港M&Aを経験。メインプロダクトである「カンリー店舗集客」の事業拡大を担うマーケティング事業部のほか、全社の財務、法務関連業務を管掌。
▼参考記事:カンリーの創業から約5年の道のり
執行役員CTO 小出 幸典
慶應義塾大学大学院修了。アクセンチュア株式会社を経て、2014年7月に株式会社Gunosyへ入社。メディアプロダクトの配信アルゴリズム開発や、全社データ基盤構築等を担当し、2019年7月にCTOに就任。2022年より業務委託としてカンリーの事業に携わり、2024年9月に執行役員CTOに就任。エンジニア部を管掌。
▼参考記事:カンリーにCTOとしてジョインしました
”サービスを作る”のではなく、”インフラになる”
宮本:
せっかくの機会なので、今のミッションになった経緯を、お聞きしたいなと。
辰巳さん(以下、辰巳):
創業前に遡るのですが、新卒では共同代表の秋山が銀行に、僕は商社に入社しました。いわば、銀行は金融のインフラ、商社はラーメンからロケットまでなんでも提供できるインフラですよね。つまり、この頃から、世界中の人々を支えるインフラを創りたいという想いがあったんです。その後、秋山と起業するときに、自分たちがインフラになれる領域ってどこだろう? と考えて立ち上げたのが、幹事代行サービスです。
当時、銀行や商社は宴会がものすごく多くて、宴会を予約するのが本当にたいへんで。この経験から、コンシェルジュ的に宴会を予約してくれるサービスを立ち上げたというわけです。さらにここで、長谷川さん(現VPoE)にジョインいただいて、テックカンパニーとしての第一歩を踏み出しました。
小出さん(小出):
最初からインフラを目指していたんですね。
辰巳:
そうですね。インフラになれる、かつ、自分たちが得意な領域を考えたら、飲食店とビジネスパーソンをつなぐインフラしかないだろうと、その当時は考えていました。
おかげさまでサービスは順調に伸びていたのですが、コロナ禍で宴会需要がほぼなくなり、事業を継続できなくなってしまいまして。一方、お客様である飲食店も窮地に追い込まれている状況を見て、まずは集客のところをなんとかしなくちゃだよね、ということで立ち上げたのが、今の「カンリー店舗集客」になります。
カンリー店舗集客は、Googleマップをはじめとする地図サービス、SNS、公式HP、各種予約サイトなど、さまざまな媒体に露出している店舗情報を一元で管理できるシステムとなっています。店舗ビジネスは「店舗の数×媒体の数」だけ管理すべき情報が増えていくため、情報の管理やデータ分析にかかる工数を削減しつつより効率的な集客に繋げていきたいという想いで開発しました。
はじめは飲食店向けを想定していたのですが、プレスリリースを出したところ、飲食店以外の店舗からの反響が想像以上に多くて。ここで「店舗に関わる人たちをすべて救えるんだ」と気づき、店舗経営を支えるインフラを創るというミッションにつながっています。
以前もお聞きした気がしますが、日本の店舗産業で働く人はどのくらいいると思いますか?
![]()
小出:
たしか、推定で2,700万人(※令和2年の産業別就業者より算出)ですよね。
辰巳:
そうです。労働力人口が約6,900万人なので、実に40%もの人が店舗産業で働いている計算になるんですね。となると、店舗DXで生産性を上げられればGDPが伸びるし、日本の産業、引いては未来を変えることだってできるかもしれない。これはぜったいにやりたい、やらなくちゃいけないと思ったんです。
小出:
カンリーは集客からスタートしていますが、商品を仕入れたり、従業員を雇ったり、給与を支払ったり、帳簿をつけたり、店舗ビジネスにおいてはさまざまな業務がありつつも、なかなかDXを進められていない店舗事業者も数多くいますからね。このすべてをカンリーはやろうとしていて、広がっていくのがおもしろそうだなと。
そこでいうと、たぶん、みんなもやりたいと思ってるんですよね。でも、やっている会社は一握りな気がしていて。僕が業務委託でジョインしたころはちょうどHR領域に進出しようとしているタイミングで、ちゃんとやっているのはいいな、と感じたのを覚えています。本気でインフラを目指しているんだな、これはすごいぞと。
その一方、当時、開発チームの人が集められなくて立ち上げがビハインドしているという話を聞いたんですね。事業を伸ばそうとしている、伸ばせるチャンスが目の前にあるのに、エンジニア組織がミッション実現に対するキャップ(上限)になってしまっているのは、もったいないなと。この部分で、自分としてできることやバリューを出せることがありそうだと感じたのが、ジョインした経緯になります。
店舗DXで、日本を、世界を変える
宮本:
店舗業務のDXを通して、どんな世界にしたいと考えていますか? 店舗そのものや店舗で働く人々、また、店舗を利用する人々にどんな影響を与えられるのかという軸で、お話しいただけると嬉しいです。
辰巳:
店舗DXはあくまでも手段であって、本当に実現したいのは店舗DXの先にある人々の幸せです。本質的でないオペレーションにとられる工数やコストを減らせれば、店舗で働く人たちの働き方や生活がよくなりますよね。そうなると、新しいメニューを開発したり、髪をカットする技術を高めたりなど、創造的な仕事に注力できるようになり、結果的に、店舗に来てくれるお客さまも幸せになる。この循環を創りたいんです。
ここで必要になるのが、データなんですね。集客やHR(採用)店舗オペレーション、物流など、店舗にまつわるデータをすべて集めて掛け合わせれば、店舗としてもカンリーとしても、できることがどんどん増えていきます。店舗から取得したデータを使って、さらに店舗に還元していくイメージですね。
小出:
情報が分断されているケースって、意外と多いですからね。たとえば、商品を作っているメーカーが「どういう人が買っているのか」を知らないことはよくあります。こうした情報を店舗とメーカーで連携できるようになれば、もっと良い商品が開発できて、消費者にも喜んでもらえますよね。
辰巳:
せっかくデータがあるのに、もったいないですよね。実はカンリーでも、まだ着手できていないことがたくさんありまして。一例を挙げると、カンリー福利厚生ではマップからお店を探せるので、どこで、どういう人が、どういうクーポンを使っているのかというデータが取れます。これを使えば、どんなお店をどこにだせば良いのか、立地戦略を立てることも可能になります。
![]()
もうひとつ、店舗ならではのところでいうと、同時性あるいは二面性(※1)ですかね。カンリー福利厚生の自社割という機能で従業員が自社の店舗を頻繁に使うようになり愛着が持てるとか、Googleマップ上で位置情報を使って採用の母集団を形成するとか。他の業界にはないデータ活用や施策をできるのは、店舗独自の価値だと思います。
(※1)同時性、二面性:よく行くお店でアルバイトをするというように、お客さまであると同時に採用の母集団にもなりうること
小出:
生活と働くということがものすごく近い位置にあって、お客さまと従業員が交差する感じがおもしろいですよね。
宮本:
今お話しされていた店舗独自の価値という軸で、もう少しお話しが聞ければと思うのですが。
辰巳:
少し飛躍してしまうのですが、店舗って、貧困をなくせると思ってるんですね。どういうことかというと、この前インドに行ってきたんですよ。水も安全に飲めない場所が多い中で、唯一、日本食レストランだけは安心して水も飲めるし、料理も食べられて、すごく幸せだなと感じたんです。
とはいっても、所得の格差などがあって、みんながこの幸せを享受できているわけではありません。じゃあどうやったらみんなが幸せになれるのかと考えると、日本食レストランと同じクオリティの店舗を増やす必要があると思うんですね。日本の店舗が持つオペレーション、安心・安全、おもてなしといったクオリティと、カンリーのテクノロジーによるDX推進。この2つを掛け合わせれば、安心・安全な食事を安く食べられるようにできるはずなんです。そのためにまずは、日本の店舗を海外に輸出する支援をしていきたいと考えています。
課題は、シナジーを生む事業、プロダクトを創ること
宮本:
ミッションの実現に向けて、やるべきことやボトルネックを教えていただけますか?
小出:
これから複数の事業領域に足を伸ばしていこうとしている中で、どのデータをハブとして使っていくのか、どうやってデータを繋げていくのかという設計を、しっかりやらなくてはならないと思ってます。
たとえばカンリー福利厚生は、クーポンを利用してくれるユーザーとクーポンを提供している(集客したい)企業をマッチングさせるプラットフォームです。マッチングアプリと同じで、片方だけ集めても事業として成り立ちませんよね。
通常、これをゼロからやるのはとてもたいへんなのですが、幸いなことにカンリーでは、「カンリー店舗集客」というマーケティング領域のツールでの取引先がありました。つまり、取引先=店舗と従業員(ユーザー)の両方がバランス良くある状態からスタートできたのが、とても良かったんですね。
さらにカンリー福利厚生では、クーポンを利用してくれるユーザー=従業員=人のデータを取得できるようになりました。このデータを使って今度は、カンリーAI面接(※2)やカンリーワーク(※3)というサービスが生まれました。簡単にまとめると、「カンリー店舗集客」で得た店舗情報により「カンリー福利厚生」事業がグロースし、「カンリー福利厚生」で得た従業員情報が「カンリーAI面接」「カンリーワーク」を開発するきっかけになったということですね。
(※2)カンリーAI面接:店舗のアルバイト採用業務に特化した面接支援サービス
(※3)カンリーワーク:店舗運営の即戦力人材のデータベース構築とスポットワーク活用サービス
![]()
辰巳:
小出さんのおっしゃるとおりで、カンリー福利厚生によってマーケティングからHRの架け橋を作れたことが、大きなブレイクスルーになりましたよね。ここから新しい領域にどう切り込んでいくのか、次の一手がめちゃくちゃ重要だと感じていて。どの領域に、どうやって繋がって、どのようなシナジーを生む可能性があるのかを見極めて、決めなくてはならないと思ってます。
次の一手を考える一方で、カンリー店舗集客も進化させるべきタイミングにきたと感じてます。カンリー集客は、媒体の一元管理や一括発信など認知拡大に強みがあるプロダクトで、新規顧客の獲得に効果を発揮します。これを維持しつつ、今後はCRM的な要素—顧客と良好な関係性を長期的に築き上げられる仕組み—を取り入れて、リピートを増やす方向に舵を切りたいと思ってるんですね。
小出:
今、辰巳さんが話してくださったような、事業をこうしていきたいという未来(理想)がある中で、どれだけ早くカタチにできるのかがエンジニアには求められているのかなと。スピードの早い業界なので、組織としていかに生産性を高めて、どれだけ早くリリースし、どれだけ早く改善していけるのか、いわば先頭を走れるかどうかが重要だと思っています。
もうひとつ、表現がちょっとむずかしいのですが、エンジニアにも仮説思考みたいなものが必要な気がしています。データを見て「こういう傾向があります」と言えるだけでなく、ビジネスドメインに対する興味っていうんですかね。店舗のビジネスがどういうものなのかとか、なんでこの行動をしたのかという仮説を立てたりみたいなことができるといいんじゃないかと。もっと端的にいうと、モノを作ったら終わり、ではなく、自分たちが作ったモノがどんなインパクト(影響)を残せているのかをイメージするといった感じでしょうか。そして、エンジニア組織としてこうした興味を持てるようにするのが僕の役割なので、丁寧に伝えていきたいなと思ってます。
/assets/images/6358952/original/2305ec05-b5a2-47e5-8d8b-19992877635b?1614908067)



/assets/images/6358952/original/2305ec05-b5a2-47e5-8d8b-19992877635b?1614908067)