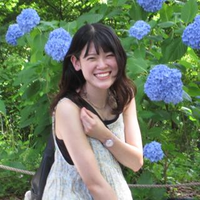こんにちは!リジョブ採用担当の上妻(こうづま)です。
この記事を開いてくれて、ありがとうございます!
今回はちょっと真面目なテーマなんですが…
「GIVER」って聞いたことありますか?
簡単に言うと、“与える人”のこと。
リジョブでは、そんなGIVERのような働き方・在り方を、すごく大切にしてるんです。
「人の役に立つ働き方ってどうやるの?」
「貢献とキャリアはどうつながるの?」
「とにかく成長したいけどどうすればいい?」
そう思ったことがある方に、ちょっとでも届いたらうれしいなと思って書きました!
そんな人や社会に価値を与えたい=GIVERをこの世の中に増やしていくために、
リジョブが取り組んでいる文化づくりや人材育成を紹介します!
★本記事の想定読者
・「利他的な働き方」また「社会課題を解決するための成長」に関心のある学生や社会人の方、成長を追い求めている方
・組織文化、マネジメントを磨きたいリーダー、人事担当者

★執筆者プロフィール★
上妻 潤己(コウヅマ ジュンキ):2019新卒入社/熊本県出身。長崎県対馬での市役所インターン及び独居高齢者との1年間の共同生活を経て、「だれもが孤立しない心豊かな世の中を創る」ことを志しリジョブ入社。ケア(旧:介護)事業部のチームリーダーを経て、現在はコーポレート推進UNITにて、新卒採用チームリーダーとして採用・組織創りにに携わる。好きな言葉は「創造的な利他主義」。
目次
0.なぜ今「GIVER」という働き方なのか?
1.GIVERになるには?
2.“誰かの役に立つ”って、実はすごくパワフルなこと
3.GIVEは“気づき”から始まる
(補)“GIVE”からはじまる社会のかたち
4.GIVERになるための「LOVE&POWER」の話
5.GIVEを可視化し、育む:真のGIVERとは?
giver賞与という仕組み
6.“GIVEの解像度”を高めるために
7.コーポレートチームから始まった“問い”
8.日常にGIVEを育てる「心づけ委員会」
9.GIVERを目指す、ひとりのわたしとして
10.GIVEが“当たり前”になる文化をどう創るか
11.結び:自分のGIVEが、誰かの未来につながる
0.なぜ今「GIVER」という働き方なのか?
「成長したい」
「もっとできることを増やしたい」
そんな想いを持っている人にこそ、届けたい考え方があります。
この社会では、「自分がどれだけ社会に価値を提供できるか」が、評価や成長の基準になります。
スキルや肩書きだけじゃなく、“誰かにとって必要な存在かどうか”が問われる時代。
つまり、「人の役に立てる力」がある人こそ、どこにいても求められるし、成長の機会が自然と集まってくる。
逆に、スキルや肩書きがあっても、それが誰かの役に立たなければ、ただの宝の持ち腐れです。
だからこそ、GIVERという在り方を目指すことが、何よりも“成長の近道”になるんです。
GIVERとは「本質的に誰かの役に立てる人」のこと。
そしてその力は、誰の中にも眠っていて、ちょっとした“気づき”から育っていきます。
1.GIVERになるには?
「誰かの役に立ちたい」
「人のためになることがしたい」
そんな気持ちを持っていても、ふと立ち止まってしまう瞬間ってありますよね。
「自分に何ができるんだろう?」
「人の役に立つ働き方ってなんだろう?」
「なんだか“いい人ぶってるだけ”に思えちゃう…」とか。
でも、僕は思うんです。
GIVEって、いきなり“誰かのために動くこと”じゃないって。
まずは、「自分が今どれだけ与えられているか」に気づくこと。
それが、すべてのはじまりだと思っています。
2.“誰かの役に立つ”って、実はすごくパワフルなこと
アンパンマンを思い出してください。
自分の顔をちぎって差し出してるのに、元気で、笑ってて、周りからも愛されてて…
(考えれば考えるほど、あの方はほんとすごいですよね。)
ここで伝えたいのは、あんぱんを差し出すことは本当に大変だよねってことなんです。
まず、「この人にとっての“あんぱん”は何か?」をちゃんと理解するのが、そもそも難しい。
本当の意味での価値提供って、相手の背景や気持ちを深く理解したり、
自分の視点を柔軟に広げたりしないとできないんですよね。
相手のことをちゃんと見ていないと、あんぱんが欲しいのにカレーパンを買ってきちゃって──
「お腹は空いてたけど、今それじゃないんだよね…」ってなる。笑
(※経験談ではありません)
つまり、“本当に誰かの役に立つ”って、それだけ本気で相手に向き合わないと届かない。
それは簡単じゃないけど、すごくパワフルなこと。
そして、もうひとつ大切なのは、
それを「無理してやること」じゃない、ってこと。
「そこまでしてでも、この人のために何かしたい」っていう、純粋な想いが自分の中にあるかどうか。
そうじゃないと、続かないし、やらされ感で疲弊してしまいます。持続可能ではないんです。
純粋な想いがあるから、怒られてでもそれでもいつかはあんぱんを届けたいって思うんです。
(※経験談ではありません)
そしてその純粋な想いがあるからこそ、こういう問いも自然と浮かんでくるんです。
「この人にとって、本当に嬉しいことってなんだろう?」
「どうすれば、この人がもっと幸せになれるかな?」
そうやって相手を思えるからこそ、表面的じゃない、本質的なGIVEが生まれるんだと思います。
3.GIVEは“気づき”から始まる
じゃあ、その“純粋な想い”ってどうやって育まれるのか?
──それは、自分が誰かから与えられていることに気づいたときなんです。
たとえば、過去に誰かに救われた。支えられた。信じてもらえた。
今も、チャンスをもらっている。力を貸してもらっている。
そう気づけたとき、人って自然と「今度は自分が返したい」と思えるようになる。
それは、義務でもないし、見返りを求めるものでもない。
本能みたいに、素直な感情として湧いてくるんです。
与えられる経験って、実は日常のなかにたくさんあります。
- 小さい頃に見守ってくれた親や先生
- 部活で支えてくれた先輩、授業で声をかけてくれた友達
- 社会人になってから、ミスをカバーしてくれた上司
- 忙しいのに時間をつくって話を聞いてくれた先輩
- いつも気にかけてくれる後輩や仲間
朝コンビニで「おはようございます」って笑顔をくれた店員さんだって、
思えば、あれも小さなGIVE。
でも、そうしたGIVEも、あまりにも自然すぎて──いや、“当たり前”だと自分が思い込んでいるだけで
気づかなくなってしまうんです。
だからこそ、「気づき」を育てることがすごく大切なんだと思います。
- 誰から、どんなGIVEをもらっているか?
- 自分は、どんなGIVEができているか?
それに気づいたり、言葉にしてみたり。
ときには「ありがとう」と、ちゃんと伝えてみたり。
そういう“気づきの循環”があるからこそ、
「今度は自分が誰かに返したいな」という気持ちが、自然と芽生えていく。
GIVERって、特別なスキルを持った人のことじゃなくて、
そういう小さな気づきを大事にしながら、日々のなかで実践している人のことなんだと思っています。
(補)“GIVE”からはじまる社会のかたち
GIVERという在り方を考えるなかで、僕自身が出会ってきた言葉や思想があります。
少しだけ、その紹介もさせてください!
特に大きな影響を受けたのが、
近内悠太さんの『世界は贈与でできている』と
影山知明さんの『ゆっくり、いそげ』という2冊の本です。
どちらも、「人と人とのつながりは“贈与”によって成り立っている」という思想を軸に、
“与える”ことの意味や、“与えられてきたことに気づく”ことの大切さを、あたたかく、でも鋭く伝えてくれます。
「交換はそこで終わるけど、贈与は続いていく」
「与えることは、“返してもらう”ことじゃない。次の誰かに“送っていく”こと。」
そんな言葉に出会ったとき、リジョブが大切にしているGIVERという概念が、
“組織の文化”を超えて、“社会のあり方”にまでつながっている気がしたんです。
4.GIVERになるための「LOVE&POWER」の話
ここまで読んでくれたあなたへ。
GIVERになるって、きっと「優しさ」と「力強さ」の両方が必要なんだと思うんです。
リジョブでは、それを**「LOVE&POWER」**という言葉で表しています。
(採用基準や日々の行動指針としてもすごく大事にしてる考え方です!)
GIVERになるために必要なのは、2つの力です。
- LOVE(気づく力)
与えられていることに感謝できる、感受性の土台。 - POWER(届ける力)
相手を解像度高く理解し、本質的な価値を形にする実行力。
この2つを高めていくことが、GIVERとして成長していくうえでのカギだと思っています。
そしてリジョブは、「GIVERとしての成長」をチームみんなで育てていける場所です。
このあと、「GIVERを可視化する仕組み」や「文化としてどう根付かせているか」をご紹介していきます!
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
5.GIVEを可視化し、育む:真のGIVERとは?
GIVERになるには、与えられてきたことに気づく「LOVE」と、価値を届けきる「POWER」が必要。
でも、それって日常の中でどう育てていけるんだろう?
──そんな問いに対して、リジョブでは“文化と仕組み”の両面から取り組んでいます。
そのひとつが「giver賞与」です。

giver賞与という仕組み
リジョブでは賞与を、個人賞与とチーム賞与に分けて運用しています。
そのうち、チーム賞与のひとつがgiver賞与。半年に一度、各チーム(=“オクリビト”)が「この半年で最もGIVEしてくれた」と感じた個人とチームを選出し、感謝の気持ちとともに賞与を贈る仕組みです。
ポイントは、「自チーム以外」を対象に選ぶこと。
つまり、自分たちとは異なる領域で働く人のGIVEに、目を向ける時間でもあるんです。
実際の選考では、さまざまな視点が飛び交います。
- 普段一緒に仕事している人に、あらためて感謝を伝えたい
- 間接的でも、自分たちの成果を支えてくれた人に贈りたい
- 顧客や社会にインパクトを生んだ取り組みにリスペクトを届けたい
こうした対話のプロセスそのものが、「GIVEとは何か?」をみんなで定義し直す時間にもなっています。
6.“GIVEの解像度”を高めるために
「何をもって“GIVE”とするか?」
これは、思っているよりずっと深い問いです。
たとえば——
・目に見える成果があったかどうか?
・自分が助かったかどうか?
・会社や社会へのインパクトにつながっているか?
こうした基準は正解・不正解ではなく、どれも一理あります。
でも大切なのは、「自分たちは、どう考えるか」を対話を通じて、すり合わせていくこと。
- 自分の役割やチームのミッションに対して、誰がどんな貢献をしてくれていたのか?
- それは、どんな価値を生んでいたのか?
- それは、自分がどうありたいかともつながっていたのか?
こうした問いを言葉にして交わすことで、
私たちの“価値提供の解像度”は、ぐっと高まっていきます。
giver賞与は、単なる評価制度ではありません。
「誰かの価値に気づく力」も、「価値を届ける力」も、日々の対話を通じて育まれていくと信じているからこそ、仕組みと文化が両輪で設計されているんです。

7.コーポレートチームから始まった“問い”
このgiver賞与も、実は最初から社内制度だったわけではありません。
はじまりは、コーポレートチームでの小さな実験でした。
賞与をメンバー全員で分配してみよう、という試みの中で出てきた、ある問い。
「電話対応って、賞与の対象になるの?」
ある人は、「目に見える成果を出した人に賞与が渡るべき」と言いました。
でも別の人は、「電話を引き受けてくれたから、自分は集中して成果を出せた」と言いました。
このやりとりをきっかけに、
“貢献”の定義が、人によってこんなにも違うんだということに気づかされたんです。
GIVEは、見えづらいことも多い。
だからこそ、ちゃんと“見に行く姿勢”が大事なんだと、このとき体感しました。
(また僕自身「賞与を決めるって、こんなにも難しいのか」と実感し、いつも賞与を決めていただいている上司や経営陣への感謝も生まれました)
8.日常にGIVEを育てる「心づけ委員会」
giver賞与のような制度だけではなく、リジョブにはもっと気軽に感謝を届け合う文化もあります。
それが「心づけ委員会」です。
形式ばらず、日常の中で感じたGIVEに「ありがとう」をメッセージで贈る。
感謝を送り合えるこの取り組みは、GIVEを可視化し、文化にしていく場になっています。
私たちは信じています。
「与えられることを当たり前にしない」文化が、「与えることを当たり前にする」土台になると、私たちは信じています。
小さな「ありがとう」が、GIVERを育てる最初の一歩だから。
(ちなみにこの他にもGIVEを育てる仕組みを画策中です)
9.GIVERを目指す、ひとりのわたしとして
ここまで書いてきたことは、リジョブの文化であり、仕組みです。
でも、それ以前に。
わたし自身が、「GIVERでありたい」と思う、ひとりの人間です。
新卒で入社したばかりの頃。
「成果を出すこと」「自分のこと」にばかり目が向いていて、周囲に迷惑をかけまくっていた日々がありました。
でもある日、ふと気づいたんです。
忙しくて、責任も重くて、きっとしんどかったはずの上司が、
それでも私のためにたくさんの時間やエネルギーを割いてくれていたことに。
その瞬間、涙が溢れました。
「こんなにも、自分は与えられていたんだ」と。
そこからは、「返す」じゃなく、「送る」ことが自分の使命なんじゃないかって思うようになりました。
今はまだ未熟だけれど、
今度は誰かの挑戦を支えられるようなGIVEができる自分でいたいと、心から思っています。
10.GIVEが“当たり前”になる文化をどう創るか
GIVEの文化を育てていく──
それは、簡単なことではありません。
GIVEって、派手じゃない。
ときに誰にも気づかれないような、小さな行動だったりします。
しかも、受け取る人の反応も明確じゃないことが多い。
そうなると、「自分ばっかり与えている気がする…」と感じて、
いつの間にか自己犠牲のようになって、苦しくなってしまうこともあります。
だからこそリジョブでは、**“自分のコアとつながったGIVE”**を大事にしています。
「何かをやらなきゃ」じゃなくて、
「自分はどう在りたいのか」から出てくる行動こそ、
疲弊しないし、誰かに伝わるものになると信じているからです。
Doingではなく、Beingから始まるGIVE。
その“あり方”を育てるために、私たちは日々の中でこんなことに取り組んでいます。
- 1on1での丁寧な対話
- 自分を見つめ直す振り返りの時間
- 意図的に自分に“余白”をつくること
- 与えたGIVEや受け取ったGIVEを振り返るリフレクションの習慣
こうした仕掛けや場づくりによって、
メンバー一人ひとりが、自分の根っこから出てくるGIVEを見つけられるように。
そして、それが自然と組織のカルチャーとして染み込んでいくように。
GIVEの文化は、“誰かの努力”だけでは育ちません。
一人ひとりが、自分のGIVEと向き合いながら、
仲間のGIVEに気づき、讃え、共に育てていくことで、少しずつ文化になると信じています。
11.結び:自分のGIVEが、誰かの未来につながる
GIVEって、特別なことじゃない。
目立つことじゃなくてもいい。
誰かにとって本当に意味のあることって、案外、小さな行動の中にあったりします。
・忙しそうな同僚に、「大丈夫?」と声をかける
・ふとした瞬間に、「ありがとう」と伝える
・相手の目線に立って、もう一歩だけ寄り添ってみる
そんな、ささやかなGIVEの積み重ねが、
いつか誰かの背中を押したり、気づきを与えたり、勇気になったりする。
だからまずは、「自分がどれだけ与えられてきたか」に気づいてみてほしい。
そして、そのバトンを、今度は“次の誰か”に渡していく。
それが、GIVERという在り方。
そしてそれは、チームや組織を育て、社会を変えていく力だと、私たちは信じています。
リジョブは、そんな“GIVEの連鎖”が自然と生まれる組織でありたい。
そして、関わるすべての人にとって、「GIVERであることが誇れる未来」を創っていきたい。
それがわたしの人生を賭けて取り組みたいことでもあります。
世の中のGIVERに乾杯🍻
改めて、ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました!!
/assets/images/4473906/original/9ecf8e27-8ce2-44fd-ab79-2a0bb371332b?1578965838)
/assets/images/4473906/original/9ecf8e27-8ce2-44fd-ab79-2a0bb371332b?1578965838)