観光客でにぎわう鎌倉の中心地から少し離れると、早春の澄んだ空気に響く小鳥のさえずりと木々に囲まれた、古民家再生オフィスがありました。深層学習技術とロボットアームを用いて、野菜を自動収穫する汎用型ロボットの開発および収穫サービスを手がけるinaho株式会社(以下、inaho)です。
今年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が実施する「MURCアクセラレータ LEAP OVER」では最優秀賞を、スタートアップの登竜門であるICCサミット「スタートアップ・カタパルト」で優勝を飾り、人手不足に悩む農家と多くの投資家から注目を集めているのがinahoの共同創業者で代表の菱木豊(ひしきゆたか)さん。
(菱木さんのプレゼンテーションは59:41〜)
「なぜ農業なのか」。その問いに菱木さんは「AIを使った事業をしたい」との思いが先にあり、たまたまその思いに合致したのが「農業」だったといいます。今でこそ全国各地の農家とネットワークを持つ菱木さんですが、元は農業とまったく縁のない仕事をしていました。
菱木さんの考え方は、私たちが「新しいこと」にチャレンジする際の道標を与えているようにも感じます。菱木さん自身のこと、inahoのこと、そしてこれから起き得る「未来の農業ビジネスの姿」にまで、話は広がりました。
「AIが来る」。時代の潮流に、今度こそ乗りたかった男の賭け
「AIを用いた事業を手がけたい」と考えた菱木さんは、ITジャーナリストの湯川鶴章さんが主催するThe Wave塾を受講。そこで、アメリカ・Blue River Technologyの「トラクターに積んだカメラが野菜の成長度合いを測定し、自動的に間引く」という開発事例を目にします。これが、現在の事業につながるアイデアとの出会いでした。
──AIに着目したきっかけは何だったのでしょうか?
「20代の中頃、有名人や経営者の自伝を読むのが好きでした。うまくいっている人、面白いことをしている人『時代の潮流をいち早くつかんでいる』ところが共通していると思ったんです。当時の自分もインターネット、モバイル、スマートフォン、アプリとさまざまな時代の潮流を感じていましたが、不動産投資の職に就いていて、それを生かせませんでした。だからこそ『次の時代の潮流は絶対につかもう』と強く思っていたんですね。そこで見つけたのが、AIだったんです」
──そう思っているときに、アメリカでの事例を目にしたのですね。
「勉強し始めると、これは絶対に時代を変えると予感できました。今から5年ほど前かな。海外では他のAI活用事例もどんどん生まれつつありました。自分ができることで、今からでもバリューを与えられることはないかと考えているときに、たまたまBlue River Technology社の活用事例を知ったんです。しかも、その翌日に鎌倉で、農家の友人と会う機会がありました。事例を話してみると『それよりも、雑草を抜いてもらいたい』といわれたのです」
──想定外の、現場のリアルな声だったと。
「『本当に困っている人がいて、かつ誰もそこに対してアプローチしている人が今のところいない』という状況だと気付き、うまくいけば大きな価値が出るはずだと、AIを用いた雑草除去ロボットの開発にトライし始めました。進めているうちに、野菜を自動収穫するロボットのほうが、ニーズ強いうえに使う頻度が高いことが分かってきたので、そちらの方へ開発の主軸を切り替えて、現在に至っています」
上振れの数字は見ずに、堅実なラインで見極める
inahoのプロダクトの方向性が変化したように、菱木さんの経歴も一本道ではありませんでした。調理専門学校を卒業するも調理の現場は肌に合わないと感じ、その道には進まず不動産投資会社へ入社。不動産投資コンサルタントとしてデータを吟味し、数字をにらみながら、顧客の投資を成功に導く仕事を4年半続けました。数字と顧客とに向き合う日々は、菱木さんが思ってもいなかった能力を、後に開花させることとなります。
──会社員時代の経験で、今に役立っていることは何ですか?
「リターンや利回りなど、数字で結果がハッキリと分かる投資の仕事は、『目利き力』が重要です。それが今の経営のいい練習になっていましたね。それこそ、ドライに数字をにらんで未来を見るのが好きなんですよ。inahoの事業計画のP/Lを作るときにも、数字の立て方は、投資コンサルタント時代の考えが反映されていますね」
──仕事のなかで、強く意識していたことは?
「マンション一棟への投資で何億円という世界でしたから、その人の人生を背負っているのと同じようなものです。『顧客には絶対に失敗させてはならない』と思うので、上振れの数字はなるべく見ずに、堅実な低めのラインにベースを置くよう意識していました。強迫観念的に(笑)」
──顧客に対しても真摯に向き合っていたのですね。
「当時の顧客とは今でも付き合いがあって、inahoの株主になってくれた方もいます。そのころから10年以上のスパンで考えて、関係をずっと構築できるようにしてきたからだと思います。そういう思いで仕事をしていたから、顧客が儲かる物件を探し当てる手間が、すごくもどかしくて。自分たちで“ベストのもの”を作って自信を持って勧める仕事をしたいという思いも強かったですね。inahoで手がけている自動収穫のプロジェクトは、解決が困難でまだ誰もやっていない、さらにリターンが見込めて、農家のみんなが解決を望んでいる。以前の仕事で追い求めたかった要素が全部重なっていました」
「選択肢がないから、途中で変えられない」という“恐怖”を越えて
ICCサミット「スタートアップ・カタパルト」で、inahoの自動野菜収穫ロボットが見事優勝を飾ったのは、この取材の直後でした。AIと農業とが菱木さんの頭で結びつき、inahoとして走り続けた5年間。いち早く始められた理由、そして続けられた理由を、菱木さんは語ってくれました。
──inahoがいち早く未踏の領域を開拓できた要因は何だったのでしょうか?
「僕が、農業についてまったくの素人であることが良かったのでしょう。答えが分からないし、自分のなかにも答えを持っていないから、現場へ行くしかない(笑)。今でも分からないときは現場へ行くし、現場の人の答えを聞くことを大切にしています。もう一つはシーズとなる技術が一切ないベンチャーだったことです。例えば、大学の研究室なら開発した手持ちの技術をいかに生かすかという話になりがちですし、農機具メーカーなら自社の製品を使うといった制約があったりします。僕らにはそれがなく、農家のニーズに対するソリューションだけを考えられるシンプルさが強みだと思っています」
──RaaS(Robot as a Service)の従量課金型ビジネスモデルも、農機具の業界ではユニークですね。
「最初は売り切りで考えていたんです。販売価格を試算したら600万ほどになったのですが、それでも買いたいという声がけっこうありましたから。ただ、農家の方が心配するのは『10年後もちゃんと使える?』とか『すごくいいものだけど、自分は65歳で、70歳で廃業するかもしれない。今から設備投資は難しい』といったことなんですね。こういうことも、現場で面と向かって初めて分かって。会社自体がまだ設立から2年ほどで、売り切りだとその要望に応えられないことが絶対に出てきてしまいます。また、売り切りモデルでは中長期的には成長の伸びが鈍るのも分かってきて、そこで半年以上毎日考え続けて『売るの、やめよう』と、ロボットの収穫量に応じて課金するRaaSにたどり着きました」
──その切り替えの「目利き」にも、投資コンサルタントの経験が生きていますね。
「何かを選ぶときに心がけているのは、それまでに選択肢をなるべく多く作っておくことです。ここはなるべく妥協せずにやります。選択の見極めはシビアに、気持ちよりも数字や将来性で見ています。雑草ロボットから収穫ロボットに切り替えたのも、将来的にはこちらのほうが跳ねるな、という伸びしろを見たからです。ちゃんとスケールしたら、それから雑草ロボットをまた再開できますし、もし、雑草ロボットしか選択肢がなかったら、途中で変えられないし、仮にしぼんでいく事業だったら会社もろともズブズブ沈むしかないですから。その怖さが、体感的に分かっている気がするんですよね」
農作業をロボットに任せられるようになったとき、農家の人手不足が解消されるだけではなく、さらに大きな新しいビジネスへとつながると、菱木さんはいいます。後篇ではテクノロジーが第一次産業を変えるという、未来への展望を伺います。

/assets/images/3534676/original/c980611d-fd67-43e7-b62e-b49ed919a6a1?1551754129)

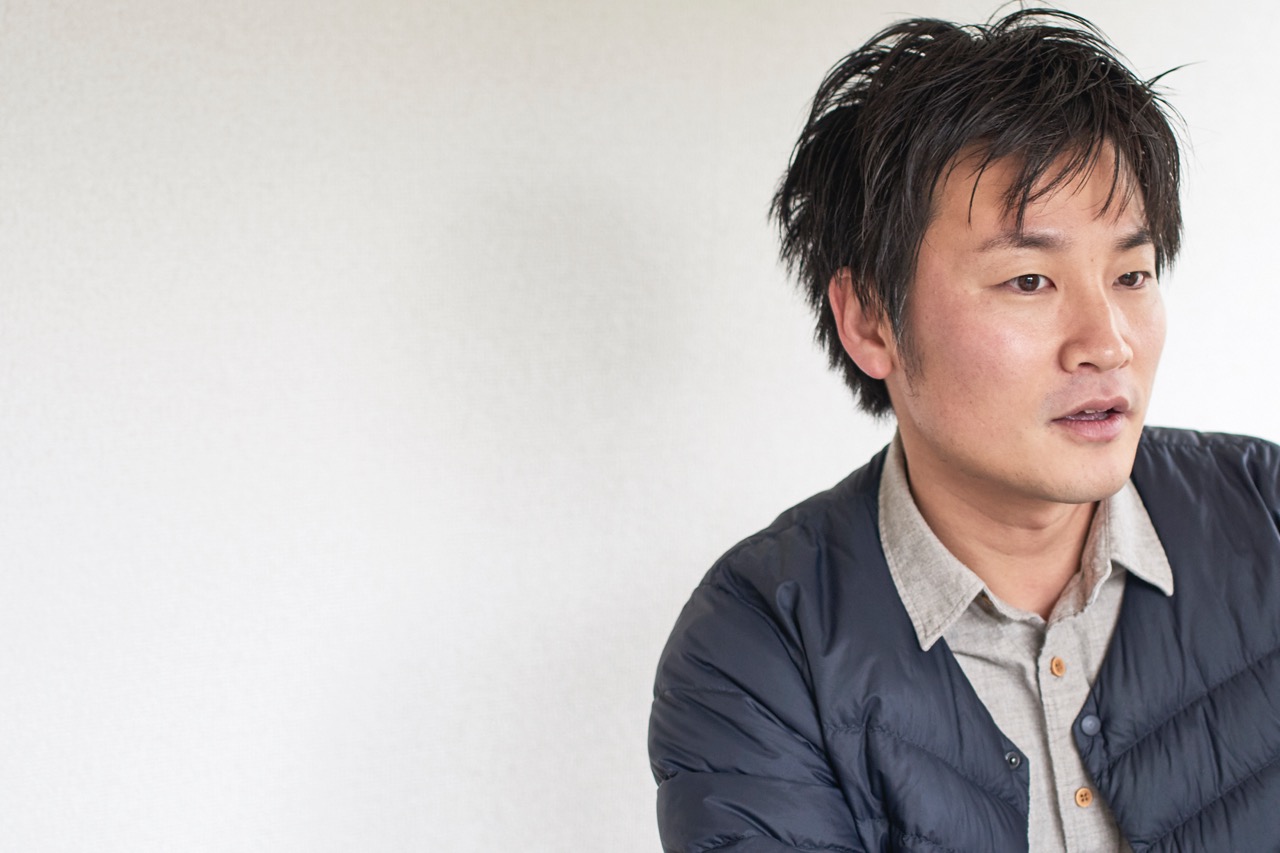





/assets/images/5110580/original/48e6a3f9-c46b-471c-ba7e-d79e2f6aaa2d?1591253669)
/assets/images/4360689/original/35e0fa2b-c6eb-4188-9827-28899b900da8?1575869551)
/assets/images/4206744/original/3ddbb4a0-48d1-48c5-8135-b35c3fca1239?1571823940)