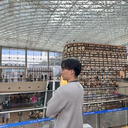DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえで、AIの存在はもはや無視できません。業務の自動化や生産性向上に加え、属人化の排除やスピード感のある意思決定にもつながります。とりわけ、DXコンサルティングでは「伝える力」が重要であり、その武器となるのがプレゼンテーション資料です。
今回、AIによって資料作成がどこまで効率化・高度化できるのかを検証すべく、2つのツールを実際に使用してみました。
今回取り扱うAIツールの紹介
1. イルシル(https://irusiru.jp/)
イルシルは、日本で開発されたAIプレゼン資料作成ツールです。特徴は、テキストを入力するだけで、構造化されたスライドを自動生成してくれる点にあります。
特に、日本の企業文化や資料スタイルにマッチしたアウトプットが得られるのが魅力です。
使用感のポイント:
- 日本企業に合ったデザインテイスト
- AIが伝えたいことを論理的に構造化してくれる
- レイアウトのセンスも良好
- ただし、デザインパターンに限りがあり、完成度はやや物足りない場面も
イルシルで生成▼

2. Canva(https://www.canva.com/)
Canvaは、世界中で使われているグラフィックデザインツールで、近年はAIによるスライド作成機能も登場しました(現在はベータ版)。
直感的な操作で多彩なデザインが可能で、特に見栄え重視の資料作りに力を発揮します。
使用感のポイント:
- 海外風の洗練されたテンプレートが豊富
- 細部までカスタマイズ可能な自由度の高さ
- AIによる自動生成の完成度は今後に期待
Canvaで生成▼

最適な使い分けは?
イルシルで構造を作り、Canvaでデザインを磨く。
この2ツールを組み合わせることで、構造化された内容と、洗練されたデザインの両立が可能になります。
例えば、まずイルシルで論理展開の大枠を作成し、それをCanvaに取り込んでデザイン性を高めると、スピード感と完成度を両立したプレゼン資料が完成します。
AIの進化は、単なる業務効率化にとどまりません。
AIツールを実際に使ってみて感じたのは、「人間が得意な構造化」や「デザインのセンス」といった分野にもAIが入り始めているということです。
これは裏を返せば、AI技術を理解し、適切に使いこなせるエンジニアの価値がますます高まることを意味します。
DXに関わるすべてのエンジニアが、AIを「ツールとして使う」だけでなく、「業務やプロセスを変える存在」として捉えることが重要です。
興味がある方は、まず気軽にイルシルやCanvaを使って、AIの可能性を体感してみてください。
/assets/images/2976948/original/556bc641-5ab2-41cf-b199-f6a579aca7ea?1583463802)
/assets/images/20930557/original/024e9ab5-7e55-4c89-b9da-f87a3db94274?1744953981)